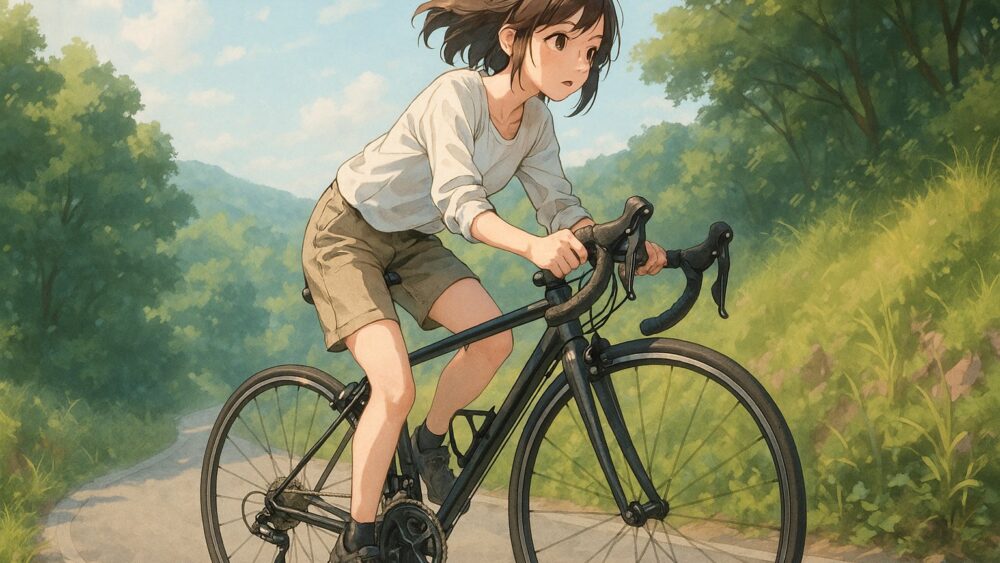ロードバイクのギア比計算は、速さや登坂のしやすさに直結する基礎です。何を基準に選ぶべきか、重要性や影響、そしてメリットとデメリットを整理しておくと迷いにくくなります。本記事では、ギア比を変えるタイミングやギア比と速度の関係、実走で役立つギア比表の読み方、精度を高めるギア比 計算方法、さらにギア比計算アプリやギア比計算ツールの使い分けまで、実務的に解説します。あわせて、汎用的なギア比おすすめ例、ギヤ比とタイヤの相互作用、用途別の選び方まで体系的にまとめ、今日からセットアップを最適化できるように案内します。
ロードバイクのギア比計算の基礎知識

- ギア比の重要性と走行性能への影響
- 登りや平地でのギア比を変えるタイミング
- ギア比と速度の関係を数値で理解する
- 初心者でも使いやすいギア比表の見方
- ギア比の計算方法を段階的に解説
- ギア比計算アプリでできることと選び方
ギア比の重要性と走行性能への影響

ギア比は、フロントの歯数をリアの歯数で割った値で表され、ペダルを1回転させたときに後輪が何回転するか、ひいては1回転でどれだけ進むかを決めます。ギア比が大きいほど一踏みで進む距離が長くなり、同じ回転数でも速度は上がりますが、そのぶん踏力が必要になります。逆にギア比が小さいほど軽く回せますが、進む距離は短くなります。このシンプルな関係が、巡航速度、登坂時の余裕、脚の疲労の仕方、心拍の上がり方など、走行性能の多くを左右します。
実際の走りでは、ギア比はケイデンスと組み合わせて考えると理解しやすくなります。速度は概算で次の式で求められます。
速度[km/h] = ギア比 × ケイデンス[rpm] × タイヤ外周[m] × 60 ÷ 1000
700Cの一般的なタイヤ外周を約2.10mとすると係数はおよそ0.126になり、ケイデンス90rpmでギア比4.55なら約51.6km/h、2.50なら約28.4km/hの目安です。ここから分かるとおり、目標速度を実現するには、ギア比を上げるか、ケイデンスを上げるか、あるいは両者の適切な折り合いをつける必要があります。
長時間の巡航や登坂を考えると、速度の達成以上に安定したケイデンスの維持が鍵になります。低ケイデンス高トルクは一踏みの力が大きくなり筋疲労や関節負荷が増えやすく、心拍は上がりにくい一方で脚の張りが蓄積しやすい傾向があります。高ケイデンス低トルクは一踏みの力が小さくなるため筋疲労は分散され、呼吸循環系への負荷にシフトします。終日走るロングライドや長い登坂では、無理なく維持できるケイデンス帯(多くのライダーでおおむね80〜95rpm)を中心に、ギア比で微調整していく考え方が有効です。
もう一つの視点として、開発距離という指標を使うと直感的に比較できます。開発距離はペダル1回転で進む距離のことで、開発距離[m] = ギア比 × タイヤ外周[m] で表されます。たとえばタイヤ外周2.10mで、50×11(ギア比4.55)の開発距離は約9.56m、34×32(ギア比1.06)なら約2.23mです。同じケイデンスなら前者は高速巡航に、後者は急勾配の登坂に適していると判断できます。
安全性やトラクションの観点からもギア比は影響します。濡れた路面の急勾配や砂利混じりの登りでは、過度に大きなギア比だと後輪に大きな駆動トルクがかかり、スリップを誘発しやすくなります。逆に下りや強い追い風でギア比が小さすぎると、脚だけが空回りして速度に脚の回転が追いつかない状態になります。いずれも走行安定性と効率を損なうため、路面や風、勾配に応じてギア比を先回りで合わせることが、結果として平均速度の向上と疲労の抑制につながります。
実務的には、次のような目安が役立ちます。下表は700C相当の外周2.10m、ケイデンス90rpmを前提に、代表的な場面とギア比の方向性を整理したものです。数値はあくまで出発点であり、脚力やコース次第で上下します。
| 走行シーン | 目安のギア比帯 | 例の歯数構成 | ねらいと効果 |
|---|---|---|---|
| 平坦の巡航主体 | 2.6〜3.1 | 50/19=2.63、52/17=3.06 | 90rpmで約30〜35km/hを狙いやすいケイデンス維持 |
| 起伏の多い郊外 | 2.3〜2.8 | 50/21=2.38、50/18=2.78 | 小刻みなアップダウンで回転を崩さず対応 |
| 長い登坂 | 1.0〜1.3 | 34/32=1.06、34/28=1.21 | 勾配で心拍と筋負荷を抑え、失速を回避 |
| 追い風・緩い下り | 3.3〜4.5 | 52/16=3.25、50/11=4.55 | 空転を防ぎ、脚の回転を速度に結びつける |
ギア比を選ぶときの基準は、単に最高速を伸ばすことではありません。走り方と路面に合わせて、狙いのケイデンスを壊さずにトルクを適切に分散できるかが判断軸になります。平坦中心なら中段のギア比が密に並ぶ構成を優先し、登坂が多いなら最小ギアを十分に確保して回転を落としすぎないようにします。こうした考え方でギア比を設計すると、同じ体力でも平均速度を高めやすく、ライド後半の失速も抑えられます。
登りや平地でのギア比を変えるタイミング

ギアを切り替える最適な瞬間は、脚が苦しくなってからではなく、状況の変化を予測した直前に訪れます。狙いは、一定のケイデンス(おおむね80〜95rpm)を保ち、トルクの急増や失速を避けることです。地形、風、信号やコーナーなどのイベントを数秒先読みし、軽いペダリング圧で素早く1段ずつ調整することで、脚への負担と機材へのストレスを最小限にできます。
坂に入る前:8〜12秒の先読みと「先行ダウンシフト」
登りの手前では、勾配が始まる8〜12秒前(速度にして路肩の目標物1〜2個分手前)を目安に、リアを1〜2段軽くします。目的は、勾配がかかった瞬間にケイデンスが10rpm単位で落ち込むのを防ぐことです。変速は一瞬ペダル荷重を抜いて行い、チェーンとスプロケットの噛み合いを滑らかにします。勾配がさらに増す見込みなら、速度が2〜3km/h落ちるごとに追加で1段ずつ軽くするイメージが安定します。
勾配変化への追従:小刻みな1段調整とクレスト越え
坂の途中で勾配が強まったら、呼吸が荒くなる前に1段ダウン。逆に緩んだら、脚が空回りしかける前に1段アップします。頂上付近(クレスト)は速度を取り戻す好機です。勾配が緩む直前に1段、緩んだ直後にさらに1段上げ、失速せずに「乗せて」越えると、下りでの伸びが違ってきます。短いアップダウン(ローラー地形)では、上りの手前で素早く軽くし、頂上を過ぎた瞬間に重くする「先行2手」のリズムが効果的です。
平坦での風対応:向かい風は軽く、追い風は重く
平坦路では、風が実質的な勾配として作用します。向かい風ではリアを1〜2段軽くしてケイデンスを85〜95rpmに戻し、トルクの上がりすぎを避けます。追い風や緩い下りでは、85〜90rpmを下回ったら1段重くし、脚の回転を速度に結びつけます。横風区間では姿勢とコース取りを優先しつつ、ケイデンスが5rpm以上ぶれたら即1段調整というルールを置くと安定しやすくなります。
下りと高速域:空転の手前で上げ、超高回転は無理に維持しない
下りでは、脚が110rpm前後まで上がるようなら1段または2段重くします。それでも回り切ってしまう場合は、無理に回し続けず空力姿勢(上体を低く)で脚を温存する判断が得策です。チェーンが斜めになりすぎるクロスチェーンは避け、前後の組み合わせを入れ替えてチェーンラインを整えると駆動効率と静粛性が上がります。
停止と再発進:段階的ダウンシフトで軽い踏み出し
信号や一時停止が見えたら、停止までの3〜4秒でリアを1段ずつ軽くし、最後は「やや軽め」で止まります。発進は中段のギアから始め、速度が出たら2〜3秒ごとに1段ずつ重くしていくと、チェーンやスプロケットへの負担が少なくスムーズです。登りでの発進が予想される場合は、止まる前に通常よりもう1段軽く準備しておくと安定します。
操作テクニック:変速は軽い踏力で、前後の「相殺シフト」を活用
・変速の瞬間は0.5秒ほど踏力を抜き、チェーンが歯に乗り替わる余地を与えます
・フロントの変速はできるだけトルクが低い場面で行い、同時にリアを2段逆方向へ動かす「相殺シフト」でケイデンスの乱れを抑えます(例:フロントをインナーに落としたらリアを2段重く)
・荒れた路面や段差の直前での変速は、チェーン外れのリスクがあるため避け、路面が落ち着いた区間で実行します
よくあるつまずきと修正法
- 勾配がきつくなってから変える:坂の標識、影の伸び、見た目の路肩勾配など「勾配の前兆」を目印に、10〜20m手前で先行ダウンを習慣化します
- 重いまま停止して発進が重い:停止前に3カウントで1段ずつ軽くする「3カウントルール」を導入します
- 追い風で脚だけ空回り:ケイデンスが85rpmを下回ったら即1段アップ、80rpm未満なら2段アップというしきい値を決めておきます
- 大トルクでの無理な前変速:緩斜面や平坦に出た直後まで待ち、前は軽い踏力でのみ操作します
ペダルが重くなってからの変速は、すでに速度とケイデンスが落ちており、体力消耗と機材ストレスが大きくなります。数秒先を読む視線配分と、ケイデンスの小さな変化に即応する1段調整を積み重ねることが、平均速度の伸びと終盤の失速抑制に直結します。
ギア比と速度の関係を数値で理解する

ペダルをどれだけ回せば、どれだけ進むのか――その関係は、簡単な式で見通しよく把握できます。前の歯数を後ろの歯数で割った値(ギア比)に、ケイデンス(1分あたりのクランク回転数)とタイヤ外周を掛け合わせると、理想条件下での速度を見積もれます。単位をそろえると、次のように書けます。
速度[km/h] = ギア比 × ケイデンス[rpm] × タイヤ外周[m] × 60 ÷ 1000
700Cロードタイヤの実測外周をおおむね2.10mと仮定すると、式中の「タイヤ外周×60÷1000」の部分は約0.126になります。つまり、速度は「ギア比×ケイデンス×0.126」でほぼ直線的に増減します。たとえばケイデンス90rpmなら、係数は 90×0.126=11.34 ですから、ギア比に11.34を掛けるだけで速度の目安が得られます。ギア比4.55では約51.6km/h、2.50では約28.4km/hという計算です。
同じ考え方で、1回のペダル回転で何メートル進むか(開発距離)も求められます。開発距離[m/回] = ギア比 × タイヤ外周[m] です。ペダル1回転でどれだけ路面を稼げるかが直感的にわかるため、登坂の余裕や平地での伸びを検討するのに役立ちます。
下表は、代表的な歯数の組み合わせについて、ギア比・開発距離・ケイデンス別速度の目安をまとめたものです(タイヤ外周2.10m、ケイデンス75/90/100rpmで試算)。数値は小数点1位を四捨五入しています。
| フロント×リア | ギア比 | 開発距離 (m/回) | 速度 75rpm (km/h) | 速度 90rpm (km/h) | 速度 100rpm (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50×11 | 4.55 | 9.55 | 43.0 | 51.6 | 57.3 |
| 50×16 | 3.13 | 6.56 | 29.5 | 35.4 | 39.4 |
| 34×28 | 1.21 | 2.55 | 11.5 | 13.8 | 15.3 |
| 34×25 | 1.36 | 2.86 | 12.9 | 15.4 | 17.1 |
| 52×36 | 1.44 | 3.03 | 13.6 | 16.4 | 18.1 |
数字の読み方は単純です。平地巡航を想定して「ケイデンス90rpmで時速35〜36km/hを保ちたい」なら、上表の50×16(ギア比3.13)前後が候補だとわかります。逆に「10%勾配でも脚を止めずに回したい」なら、ケイデンス70〜90rpmで時速一桁台~十数km/hが出る軽いギア(例えば34×32や34×34といったギア比1.0〜1.1台)を確保しておくと現実的です。
速度はギア比とケイデンスに対して比例します。ケイデンスを10%上げれば、同じギア比で速度も約10%伸びます。したがって、トップ側の歯数を上げるだけでなく、得意な回転域(多くのライダーで80〜95rpmが目安)を安定させるトレーニングも、平地の巡航や登坂のタイムに直結します。
実走では、空気抵抗・路面抵抗・風向き・勾配変動・姿勢変化などで必要パワーが変わるため、表の値はあくまで理論上の目安です。それでも、狙う速度域から逆算して「必要なギア比」を先に決める発想に切り替えると、フロントとリアの歯数選び、さらにはリアスプロケット段間の刻み幅まで、迷いなく整理できます。タイヤを太くしたり銘柄を変えたりした場合は、サイクルコンピュータのタイヤ周長と計算の前提となる外周値を更新し、再度同じ手順で見直すと、机上と実走のズレを小さくできます。
初心者でも使いやすいギア比表の見方

同じ速度でも楽に回せるか、脚が重く感じるかは、いま選んでいる歯数の組み合わせで大きく変わります。ギア比表は、その見通しを一目で把握するための地図のようなものです。横軸にフロント(チェーンリング)の歯数、縦軸にリア(スプロケット)の歯数を並べ、交点に「フロント÷リア」で求めたギア比が入ります。まずは表のどこを見れば判断できるのか、使い方を段階的に整理します。
ギア比表の基本構造と読み方
- フロントが大きく、リアが小さいほど数値(ギア比)は大きくなり、踏み応えは重く速度は伸びやすくなります(例:50×11=4.55)。
- フロントが小さく、リアが大きいほどギア比は小さく、軽い踏み心地で登りに向きます(例:34×28=1.21)。
- 表の同じ列(同じフロント)で上にいくほど軽く、同じ行(同じリア)で右にいくほど重くなります。表をなぞると、いまの変速位置が「どのくらい軽い/重い」かを定量的に把握できます。
判断の軸は3つだけ
- 最大側の余裕(アウター×小リア)
追い風や下り、集団走で脚が空回りしないかを確認します。目安は、巡航ケイデンス(多くのライダーで80〜95rpm)を保ったまま、伸ばしたい最高速度に届くギア比を持っているかどうか。表の右上の数値が、狙う速度に対して十分かを見ます。 - 最小側の確保(インナー×大リア)
登りで回し続けられるかが焦点です。勾配8〜12%が想定されるなら、ギア比1.0〜1.2台を確保しておくと、ケイデンスを落としにくくなります。表の左下の数値が、この範囲に入っているかを確認します。 - 中段の刻み(よく使う帯域の密度)
最も長く使う速度域で、1段上げ下げの差が大きすぎないかを見ます。隣り合うリア歯数の増減率(例:12→13は約+8.3%、15→17は約+13.3%)が大きいほど、ケイデンスが乱れやすくなります。平坦主体なら12〜17Tあたりの並びが細かいカセット(クロスレシオ)が快適です。山岳主体は末端の大きい歯(32Tや34T)を優先しつつ、中段の穴(歯数飛び)が少ない配列を選びます。
3ステップで失敗しない使い方
- 自分の巡航レンジを書き出す
よく走る速度帯(例:28〜33km/h)と普段のケイデンス帯(例:85〜95rpm)を決めます。これだけで、必要なギア比の目星がつきます。速度[km/h] ≒ ギア比 × ケイデンス × 0.126(700C想定)を使い、必要ギア比を逆算します。 - 表で「縦帯(リア側)」を選ぶ
逆算したギア比に近い交点が、フロント50Tや52Tでリア何Tに位置するかを確認。近い数値が連続して並ぶ縦の帯が、あなたの巡航に合うリア側ゾーンです。ここが細かく刻まれているカセットを選ぶと、回転を崩さず速度調整できます。 - 両端のチェックで完成度を上げる
同じ表で右上(トップ側)が不足していないか、左下(ロー側)が十分かを再確認。どちらかが明らかに不足する場合は、フロントの歯数を1段大きく(小さく)する、またはカセットの上限(下限)歯数を見直すとバランスが整います。
初心者がつまずきやすいポイントと回避策
- 数字の大きいところだけを見る
トップやローの極端な数値に気を取られがちですが、実際に最も長く使うのは中段です。表の中央帯で、連番の歯数がどれだけ詰んでいるかを重視します。 - 歯数構成の「飛び」を見落とす
11-28(例:11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28)は15→17で一段飛びが発生します。このあたりをよく使うなら、11-30や12-25など他の配列で中段の密度を比較します。 - チェーンの斜め掛けを前提にする
50×28や34×11のような極端な斜め掛け(クロスチェーン)は、摩耗や変速性能の低下につながります。表を見るときも、実用域は「アウター×中〜小リア」「インナー×中〜大リア」の帯に限って評価すると現実的です。
具体例でイメージを固める
平坦を主に走り、ケイデンス90rpmで時速30km/h前後を保ちたい場合、必要ギア比はおおよそ 30 ÷(90×0.126)=約2.65 です。表から、50×19(2.63)や48×18(2.67)などが該当帯になります。この帯の上下1〜2段も近い数値で並ぶカセットを選べば、信号や微妙な勾配変化に対して、ケイデンスを崩さず対応できます。加えて、登坂を想定するなら左下隅に1.0〜1.2台のギア(例:34×32や34×34)が確保できる配列を選ぶ、という順で詰めていくと齟齬が生まれにくくなります。
カセット選びの目安(用途別の視点)
- 都市部の通勤・街乗り:11-28や12-25など、中段の連続性を優先。ストップ&ゴーに強く、再加速が滑らかになります。
- ロングライド平坦主体:11-28や11-30で中段密度とトップの伸びを両立。向かい風・追い風の変化にも合わせやすくなります。
- ヒルクライムや山岳:11-32や11-34でロー側を拡張。表の左下に十分軽いギアがあるかを最優先し、中段の穴が少ない配列を選びます。
ギア比表は「どの速度域を、どれだけ細かくカバーできるか」を可視化する道具です。日常の速度・ケイデンス・登りの傾向を先に決めたうえで表を読み解くと、数字の羅列が走りの設計図に変わります。表で中段の帯を固め、両端の余裕を確認する――この順番を守るだけで、初めてのカセット選びでも大きな外れを避けられます。
ギア比の計算方法を段階的に解説

ギア比の決め方は、思いつきで歯数を選ぶよりも、一定の手順で数値から絞り込むほうが確実です。ここでは、必要な情報をそろえる準備から、目標速度・ケイデンスに合う歯数の算出、カセット構成の最終調整までを、再現性のある手順で示します。数式は最小限にしつつ、計算の意味と使いどころを具体例で補います。
準備:前提条件をそろえる
- タイヤ外周を決めます
700Cで一般的なロードタイヤは外周約2.10mが目安です。実測やサイクルコンピュータの周長設定値があるなら、その数値を優先します。外周が変わると計算結果の速度も等比で変わります。 - 走り方の前提を決めます
平坦の巡航、短い登り、長い登り、ダウンヒルなど、よく走る場面を3つ程度に分け、それぞれで保ちたいケイデンスの範囲(例:巡航85〜95rpm、登り75〜90rpm)を決めます。 - 使うチェーンリングの候補を決めます
ロードでは52/36、50/34、48/31、46/30などが代表的です。既存のクランクを活かすのか、変更可なのかを先に決めておくと後工程が楽になります。
ステップ1:必要ギア比を逆算する
速度とケイデンスから、必要なギア比を求めます。
速度[km/h] ≒ ギア比 × ケイデンス[rpm] × タイヤ外周[m] × 60/1000
700C外周2.10m(係数0.126)なら、
必要ギア比 ≒ 速度 ÷(ケイデンス × 0.126)
具体例:
- 平坦巡航30km/hを90rpmで保つ → 必要ギア比 ≒ 30 ÷(90×0.126)=約2.65
- 平坦で40km/hを95rpm → 約3.34
- 6%勾配を12km/hで80rpm → 約1.19
この時点で、あなたの走りに必要なギア比の「点」(巡航・高速・登坂の各ターゲット)が数値で置けました。
ステップ2:ギア比を歯数に落とし込む
同じギア比でも組み合わせはいくつもあります。前提のチェーンリングを基準に、必要なリア歯数を計算します。
必要リア歯数 ≒ フロント歯数 ÷ 必要ギア比(四捨五入)
具体例(フロント50/34を想定):
- 巡航用2.65 → 50 ÷ 2.65 ≒ 18.9 → 19T前後(50×19=2.63が近似)
- 高速用3.34 → 50 ÷ 3.34 ≒ 15.0 → 15T(50×15=3.33)または52×16(3.25)
- 登坂用1.19 → 34 ÷ 1.19 ≒ 28.6 → 28〜29T(34×28=1.21、34×29=1.17)
この計算で、必要なリア側の「要所の歯数」が見えてきます。
ステップ3:カセット候補を設計する
現実のカセットは11-28、11-30、11-32、11-34などの規格品です。ステップ2で得た要所の歯数が含まれ、かつ中段の刻みが細かい配列を候補にします。中段の使い勝手は「段間差」で評価できます。
段間差(同チェーンリング内)=(次のリア歯数 ÷ 現在のリア歯数 − 1)×100%
例:14→15は約+7.1%、15→17は約+13.3%。数値が小さいほどケイデンスを乱しにくく、平坦の速度調整が滑らかになります。
比較の考え方:
- 平坦主体:12〜17T付近の段間差が小さい配列(例:11-28、11-30の中段)を重視
- 山岳主体:末端の32Tや34Tを確保しつつ、中段の飛び(15→17など)が少ない並びを優先
ステップ4:トップとローの妥当性を検証する
極端側も数値で確認します。
- トップ側(アウター×小リア)で「回し切ってしまう」速度が、想定する下りや追い風の巡航に対して十分か。例:50×11(ギア比4.55)×90rpm×0.126 ≒ 51.6km/h。これ以上を頻繁に狙うなら、52Tや10Tトップの採用も検討対象です。
- ロー側(インナー×大リア)で登りの最低速度でも回し続けられるか。例:34×34=1.00では、80rpmなら速度 ≒ 1.00×80×0.126=約10.1km/h。平均9km/h前後の急勾配を長く登るなら、34×36(1.06未満にはならないが近づく)やサブコンパクトの導入が選択肢になります。
ステップ5:実走データで微調整する
計算は出発点に過ぎません。実走で「狙いのケイデンスから外れやすい場面」を洗い出し、次の順で対処します。
- 中段の穴を埋める配列に変更(例:11-28→11-30で16Tや18Tの並びを最適化)
- 登坂で回り切れない → ロー端を拡張(11-30→11-32/34)
- 下りや追い風で回し切る → フロントを52Tへ、またはトップ10Tのカセットへ
小変更で目的を満たせることが多いため、短所が出た状況を具体的に記録してから手を入れると無駄がありません。
ステップ6:互換性とメカニカル制約を確認する
変速機には最大スプロケット歯数とトータルキャパシティという制約があります。
トータルキャパシティ=(フロント最大−最小)+(リア最大−最小)
例:50/34(差16)× 11-34(差23)→ 合計39。リアディレイラーが39Tまで対応なら適合します。最大スプロケットも34T対応かを個別に確認します。ここを満たさないと、計算通りでも実装できません。
まとめ:数値から「使える配列」へ落とす手順
- タイヤ外周・ケイデンス帯・走行シーンを決める
- 必要ギア比を逆算(例:30km/h×90rpm → 2.65)
- フロントを基準に必要リア歯数を算出
- 市販カセットの並びで中段の段間差を評価
- トップとローの妥当性を速度で検証
- 実走ログで弱点箇所を特定し、最小変更で補正
この順に進めると、数字遊びではなく走行目的に合った歯数が手早く定まります。巡航・加減速・登坂の各場面でケイデンスを安定させられる配列を選べば、疲労の蓄積が抑えられ、結果的に平均速度の底上げにつながります。
ギア比計算アプリでできることと選び方

ギア比計算アプリは、歯数とケイデンスから速度を求めたり、その逆を瞬時に計算し、走行場面ごとの最適な段を可視化できる実用ツールです。紙の早見表では追いつかない比較や、複数ホイールの外周差の管理、カセット交換時の段間差チェックまで一括でこなせます。ここでは、アプリで何ができるのか、そして失敗しない選び方の基準を具体的に解説します。
アプリでできる主なこと
- 相互変換の即時計算
速度・ケイデンス・ギア比(三者)のうち二つを入れるだけで残り一つが求まります。例えば、ケイデンス90rpmで30km/hを出すにはどの歯数が適切か、逆に50×19で回すと何km/hになるかを一瞬で確認できます。 - 全段の速度帯の一覧表示
選んだチェーンリングとカセットの全組み合わせが表やグラフで並び、各段の想定速度が見られます。よく使う中段で段間が詰んでいるか、ロー端やトップ端が足りているかが直観的に判断できます。 - 段間差とケイデンス変動の見える化
14→15のような隣接段で何%ギア比が変わるか、シフト一回でケイデンスがどの程度上下するかを数値やヒートマップで把握できます。平坦主体の配列選びで特に役立ちます。 - 複数プロファイルの保存
ホイールA(25C)とホイールB(32C)で外周を分けて保存し、ワンタップで切り替えられます。イベントごとに「山岳」「クリテ」などプロファイルを作っておくと準備が効率化します。 - 単位・指標の切り替え
開発距離(1回転で進む距離)、ギアインチ、ギア比などの表記を切り替えられます。意味合いは異なりますが、どれも歯数と外周から導かれる等価な指標です。慣れた指標で見れば理解が早まります。 - カスタムカセット編集
手持ちのスプロケット構成(たとえば12-13-14-15-17-19…のような実在配列)をそのまま登録し、既製品と並べて比較できます。1枚だけ歯数を入れ替えたときの段間差の変化も即時に確認できます。 - オフライン計算・ファイル出力
電波の弱い場所でも計算でき、スクリーンショットやCSVで出力しておけばメカ作業時のメモとしても活用できます。
選び方:必須機能と評価基準
アプリの良し悪しは、計算機能そのものよりも「入力のしやすさ」と「比較のしやすさ」で決まります。次の観点でチェックすると失敗しにくくなります。
- 入力と表示
歯数・外周・ケイデンスの入力が少ないタップで完了し、結果が1画面に収まること。屋外でも見やすい大きめフォントと高コントラスト表示があると便利です。 - 相互変換の柔軟性
速度固定モードとケイデンス固定モードの両方をワンタップで切り替えられること。途中で条件を変えても入力が保持されると比較が速く進みます。 - プロファイル管理
ホイール外周とバイク(クランク・チェーンリング)を複数保存でき、名称を付けて整理できること。イベント前のセットアップが安定します。 - 比較ビュー
候補のカセットを横並びで表示し、段間差や開発距離の差分を色分けする機能があると、実走に近い観点で優劣を判断しやすくなります。 - カスタム編集
既製の11-28などだけでなく、個別の歯数を自由に登録できること。現実のスプロケット構成に忠実に検証できます。 - オフライン・権限
計算は基本的に端末内で完結するため、オフライン対応が望ましいです。位置情報や個人情報の権限を要求しない設計のほうが安心して使えます。 - 互換性メモ
最大スプロケットやトータルキャパシティの参考値をメモできる欄があると、現実に組めるかどうかを同時に判断できます。
| 評価項目 | 必須度 | 目安となる基準 |
|---|---|---|
| 速度・ケイデンス相互変換 | 高 | 速度固定/ケイデンス固定を即時切替 |
| 全段一覧と段間差表示 | 高 | ヒートマップや%表示に対応 |
| プロファイル保存 | 中 | ホイール外周・車体を複数保存 |
| カスタムカセット | 中 | 任意の歯数列を作成・編集 |
| オフライン動作 | 中 | 計算は完全オフラインで可 |
| 画面の視認性 | 高 | 屋外で見やすいUIと大きな数値 |
使いこなしの実例:目的から逆算して歯数を当てる
- よく走る場面を三つ挙げます(平坦巡航、短い急坂、下り追い風など)。
- それぞれで保ちたいケイデンスを設定します(例:平坦90rpm、登り80rpm)。
- 目標速度を入れて必要ギア比を出し、近い段をアプリ上でマーキングします。
- マーキングした段が実際のカセット配列に含まれているか、中段の段間差が大きくなっていないかを比較ビューで確認します。
- ロー端とトップ端が不足するなら、ロー拡張のカセットやフロント歯数の変更も含めて再計算します。
例えば、外周2.10mで「30km/h×90rpm」なら必要ギア比は約2.65です。アプリで50/34×11-30の全段表を開き、2.6前後に重なる段(50×19=2.63、50×18=2.78など)を確認すれば、巡航時に多用する段が中段に集まっているかが一目でわかります。
よくあるつまずきと回避策
- 外周の未更新
タイヤを25Cから28Cに替えたのに外周が古いままだと、速度換算が数%ずれます。まずホイール周長を最新に更新してから比較します。 - 単位の取り違え
ケイデンスの入力がrpmではなく小数のrps(秒間回転数)になっているケースがあります。表示単位を確認し、rpm表記で統一します。 - 計算値と実走の差の放置
風、路面抵抗、姿勢の違いは計算に含まれていません。実走で「重い・軽い」の違和感が出た箇所をメモし、その場面の速度とケイデンスをアプリに戻して段間差を見直します。 - 互換性の見落とし
リアディレイラーの最大スプロケットやキャパシティを超える構成は、計算上よくても現実には組めません。機材側の仕様メモを併用すると安全です。
どのレベルのサイクリストにも有益な理由
初心者には、どの段を使えば楽に回し続けられるかの目安が明確になります。中級者には、中段の段間差を詰めることでケイデンスの乱高下が減り、長距離での失速を防ぎやすくなります。上級者には、コースプロファイルごとにプロファイルを切り替え、追い風や下り限定のトップ側拡張など目的別の最適化を短時間で検証できる点が強みになります。
このように、ギア比計算アプリは単なる計算器ではなく、走行目的に合わせた歯数設計と検証を反復的に支える設計支援ツールとして機能します。選定時は上記の評価基準を満たし、実走での検証と往復できる操作性の高いものを選ぶと、結果的に疲労の抑制と平均速度の底上げにつながります。
ロードバイクのギア比計算に役立つ実践情報

- ギア比計算ツールを使った効率的な分析
- ギア比のおすすめ設定と活用シーン
- ギヤ比とタイヤ径の組み合わせによる違い
- 初心者から上級者までのギア比の選び方
- 総括:ロードバイクにおけるギア比計算の活かし方
ギア比計算ツールを使った効率的な分析

ブラウザ上のギア比計算ツールは、入力した歯数から全段のギア比と速度域、必要ケイデンスを即時に可視化できるため、勘ではなく数値で最適解に近づけます。狙いは、よく使う速度帯でケイデンスを乱さずに走れる段配列を見つけ、登坂用の最小ギアとトップ側の伸びを同時に満たす構成へ落とし込むことです。
事前にそろえるデータ
まずは、次の前提をツールに正しく入れると計算の信頼性が上がります。
- タイヤ外周の実測値(例:700Cで約2.10m。サイコンに設定している周長と揃えます)
- フロントチェーンリングの歯数(例:52/36、50/34)
- 候補のリアカセットの歯数配列(例:11-28、11-30、11-34)
- 評価したいケイデンス帯(例:登り70〜85rpm、巡航85〜95rpm、スプリント100〜110rpm)
速度の計算式は「速度[km/h]=ギア比×ケイデンス[rpm]×タイヤ外周[m]×60/1000」です。外周2.10mでは係数0.126となり、ケイデンス90rpmなら係数は11.34に相当します。
分析の進め方(5ステップ)
- 現状のセットを入力し、普段のケイデンスで各段の速度を一覧表示します。巡航域で何段連続して使えるかを確認します。
- 比較したいカセットを横並びにし、同じフロント・同じケイデンス条件で速度表を重ねて見ます。
- 中段(よく使う速度帯)に注目し、1段変速での速度差(あるいは必要ケイデンス差)が小さい方を優先します。
- ロー側の拡張幅を確認します。ケイデンス70〜85rpmで想定勾配を回せる最小ギアが確保できているかを見極めます。
- トップ側の上限を点検します。追い風や緩下りで脚が空回りしないか、ケイデンス100〜110rpmで必要な最高速度を賄えるかを数値で確認します。
可視化を活かすコツ
速度ヒートマップ(色の濃淡で速度域を可視化)や、段間差(隣接段のギア比差)を数値表示できるツールを選ぶと判断が速くなります。中段が濃い帯で連続しているほど巡航が楽になり、ロー端がしっかり伸びていれば急勾配でも失速しにくくなります。段間差は、巡航域で6〜8%程度に収まるとケイデンスを保ちやすく、登坂域では10〜14%でも受け入れやすい傾向があります。
判断基準の目安(数値のしきい値)
次の指標を「合否ライン」として使うと迷いにくくなります。
| 指標 | ねらいの目安 | 解釈のポイント |
|---|---|---|
| 中段の段間差 | 6〜8% | 1回のシフトでケイデンス変化が約5〜7%に収まる |
| 登坂域の段間差 | 10〜14% | 低速域はトルクが効くため多少の粗さは許容 |
| 巡航の連続段数 | 4〜6段 | 25〜35km/hを連続段でカバーできるか |
| 最小ギア速度(90rpm) | 11〜13km/h | 34/32(比1.06)で約12.0km/h、34/34で約11.3km/h |
| 最高ギア速度(90rpm) | 47〜52km/h | 50/12で約47.3km/h、50/11で約51.6km/h |
| ケイデンス許容幅 | ±10rpm | 同じ速度で2段分の調整余地が確保できるか |
※タイヤ外周2.10m、ケイデンス90rpmの例。外周や狙うケイデンスに合わせて再計算します。
ミニケーススタディ(50/34を前提に比較)
フロント50T、タイヤ外周2.10m、ケイデンス90rpmで中段を確認します。
- 50/19は約29.8km/h、50/18は約31.5km/h、50/17は約33.3km/h、50/16は約35.4km/h、50/15は約37.8km/hです。
- 50/17→50/16のシフトではケイデンスは約6.3%低下、50/16→50/15でも約6.7%低下に相当します。これは巡航域の段間差6〜8%の目安に合致し、速度を刻みやすい配列です。
- 11-28はトップ側に単歯刻みが並び、中段の密度が高くなりがちです。11-30は終盤に24、27、30などの粗いステップが入り、登坂の維持に寄与します。11-34はロー端が伸び、ケイデンス70〜80rpmでも失速を防ぎやすい反面、中段のいくつかで段間が広がる場面が出ます。
以上を踏まえると、平坦主体なら11-28、起伏主体なら11-30、山岳や長い激坂を想定するなら11-34が候補になり、ツール上の「巡航帯の連続段」と「最小ギアの速度」を見ながら使い分けるのが合理的です。
よくある落とし穴と対策
- タイヤ外周を既定値のままにして速度が実走と合わない
→ タイヤを替えたら外周を更新し、再計算します。 - 中段の密度だけを見てロー端が不足する
→ 最小ギアの速度と想定勾配での回転数を必ずチェックします。 - 段間差の%ではなく歯数の見た目に引っ張られる
→ 50/17→50/16の1歯差は約6%、一方で25→28の3歯差でも比率では約12%など、比率で比較します。 - ツール上は最適でも実機の互換性を失念する
→ リアディレイラーの最大スプロケット歯数とトータルキャパシティ、チェーン長をメーカー仕様で確認します。
実走での検証
ツールで決めた構成は、実走でログを取り、よく通る速度帯のケイデンス分布とギア使用頻度を見返します。巡航で同じ段に固着しているならトップ側を見直し、登坂で70rpmを大きく割る場面が多いならロー側を拡張します。数値と走行感のギャップを埋めるサイクルを1〜2回回すだけで、無理のない最適解へ近づきます。
ツール選びの指針
市販・無料ツールは多数ありますが、着目すべきは「表示の仕方」と「カスタマイズ性」です。
- 速度表形式:各段の速度を一覧化できる。普段の巡航速度で段差を一目で把握可能。
- ヒートマップ形式:色の濃淡で「速度帯の密度」を直感的に理解できる。
- 段間差の数値表示:隣接段で何%の変化があるか自動算出。感覚では見落とす部分を定量化できる。
- 複数セット比較機能:候補カセットを並列表示し、平坦/登坂向けの違いを明確にできる。
- ケイデンス可変:90rpmだけでなく、70〜110rpmなど任意の範囲を同時に確認できる。
このような機能が揃ったツールなら「仮想的なシミュレーション」が短時間で可能になり、部品購入前に適合可否や性能傾向を把握できます。
効率分析をさらに進める応用例
- トレーニング計画との連動
FTPやLSD領域など、狙う心拍・出力ゾーンに合った速度帯がどの段で得られるかを確認します。例えば、心拍ゾーン2で巡航したい速度が「28〜32km/h」であれば、その範囲を複数段でカバーできるカセット構成を優先できます。 - イベント・コースごとの最適化
ブルベやヒルクライム大会など、特定コースに合わせてシミュレーションすると効果的です。平均勾配や下り区間の長さに応じ、登坂用に34Tを確保するか、巡航用にトップ側を密にするかの判断材料になります。 - ギア構成変更の費用対効果の試算
同じフロントを維持してリアカセットだけ変える場合と、フロントをコンパクト化する場合とで、速度表にどれほど差が出るかを数値で比較可能です。これにより「数千円のカセット交換」で十分か、「フロントクランクも換装すべきか」の合理的判断ができます。
まとめ
ギア比計算ツールを使った分析は、単なる机上計算にとどまらず、実走に直結する「数値による再現実験」です。速度表と段間差を視覚化すれば、どの構成が日常の走行スタイルやイベントの要求に合致するかを短時間で判別できます。さらに、ヒートマップや比較機能を活用することで「中段の密度を取るか、ロー側の余裕を取るか」といった迷いも、数値で整理しやすくなります。結果として、購入やセッティングの失敗を避け、走行効率と快適性を両立した選択に近づけるのが、このアプローチの最大の強みです。
ギア比のおすすめ設定と活用シーン

用途ごとに最適な歯数配列は異なります。ここでは、タイヤ外周を2.10m、ケイデンスの基準を90rpmとしたときのイメージを併記しながら、よくあるシーン別に実用的な組み合わせを提案します。個々の脚力や地域の勾配、集団速度によって最適解は変化しますので、あくまで出発点としてお使いください。
シーン別おすすめ早見表
| シーン | 代表的なフロント | 代表的なリア | 最小ギア比の目安 | ねらいと特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 都市部の通勤・街乗り | 50/34 | 11-28 または 11-30 | 1.21〜1.13 | 発進と信号再加速を軽くし、中段の刻みを確保します。トップ側は過不足なく、低速~中速域で扱いやすい配列が中心です。 |
| ロングライド(平坦主体) | 52/36 | 11-28 | 1.29 | 巡航域の段差を小さくし、追い風で踏み増せるトップを確保します。中段の密度を重視し、疲労を抑えながら一定ペースを維持します。 |
| 起伏の多い郊外 | 50/34 | 11-32 | 1.06 | 登坂でケイデンスを落としにくいロー側の余裕と、平坦で十分なトップを両立します。速度変化の多い地形で扱いやすい構成です。 |
| 本格ヒルクライム | 50/34(軽さ優先なら 46/30) | 11-34 | 1.00(46/30×34で0.88相当) | 勾配の強い区間で脚と心拍に余裕を残すため、1.0前後の最小ギア比を確保します。勾配10%超や長時間の登坂ではより軽い選択が有効です。 |
| クリテリウム・周回レース | 52/36 | 11-25 または 11-28 | 1.44〜1.29 | 中段の密度を最大化し、加減速の連続に素早く対応します。トップ側の伸びとコーナー立ち上がりの軽さのバランスを取ります。 |
| タイムトライアル/トライアスロン(高速巡航) | 54/40 もしくは 52/39 | 11-28 | 1.39〜1.43 | 高速域の余裕と中段の微細な刻みを重視します。向かい風区間に備えて、最低限のロー側も残します。 |
表の「最小ギア比」は、インナーチェーンリングとカセット最大歯の組み合わせを前提にした目安です。例えば 50/34×11-34 なら最小ギア比は 34/34=1.00、52/36×11-28 なら 36/28≈1.29 となります。
シーン別選定の考え方
都市部の通勤・街乗りでは、停止と発進が多いため、最小ギア比は1.1〜1.2台を確保すると楽にこなせます。トップ側の過剰な拡張は出番が少ないため、中段の密度を優先し、11-28や11-30など段間差の小さい配列を選ぶと脚の回転が整います。
ロングライドの平坦主体では、平均速度帯で1段変速の速度差が小さくなる構成が有利です。52/36×11-28は中段の密度が高く、追い風時にはトップ近辺で速度を伸ばす余地があります。長時間の走行では同じケイデンスを保ちやすいことが疲労軽減につながります。
起伏が続く郊外路では、登坂直前に軽くして回転を維持し、ピーク後に素早く上げ直せることが重要です。50/34×11-32であれば、最小ギア比1.06により勾配変化へ先回りして対応でき、平坦の巡航にも十分なトップ側が残ります。
本格的なヒルクライムでは、勾配や距離、気温による心拍・出力の変動に備えて最小ギア比を1.0前後に設定します。長い激坂や疲労蓄積を想定するなら、フロントを46/30に落として 30×34=0.88 付近まで軽くする選択もあります。軽すぎると感じる場面があっても、登坂で回転を守る保険として機能します。
クリテリウムや周回レースでは、コーナーの立ち上がりで素早く加速し、直線で踏み切る場面が交互に訪れます。11-25は段間差が小さく、回転の維持が容易です。コースが広く速度域が高い場合は11-28にしてトップ側の余裕を持たせると、風向きの変化にも対応しやすくなります。
タイムトライアルやトライアスロンでは、高速で一定ペースを刻むことが目的です。54/40×11-28などトップ寄りの構成は、回転を落としすぎずに速度を維持できます。向かい風や微登りに備えて36〜40Tのインナー側も活かせるよう、ロー側の末端は28T程度を残すと失速を防げます。
数値で見るトップとローの「効き方」
トップ側の伸びは、同じケイデンスでの理論速度を高めます。タイヤ外周2.10m、ケイデンス90rpmの場合、50/11(ギア比4.55)は約51.6km/h、52/11(ギア比4.73)は約53.6km/hの目安です。下りや追い風で脚が回り切る場面を減らし、巡航の上限を押し上げます。
一方、ロー側の拡張は、登坂時のケイデンス維持に直結します。34/34(ギア比1.00)と34/32(1.06)の差はわずかに見えても、長い登りでは脚への負担に明確な差が生まれます。目標ケイデンス70〜90rpmを軸に、失速しない最小ギア比を確保すると、心拍の乱高下を抑えられます。
1x と 2x の使い分け
一般的なロードでは2x(ダブル)が主流で、中段の密度を高く保てます。近年は1x構成も増えていますが、同じトップとローの幅を確保するためにはカセットのワイド化が必要になり、中段の段間差が広がりがちです。信号の多い都市部や変化の少ないTTでは1xでも運用しやすい一方、起伏の多いコースでは2xのほうが回転域を細かく調整しやすい傾向があります。
ケイデンスの基準と風・勾配の影響
ケイデンス90rpm前後は多くのサイクリストにとって無理が生じにくい回転域です。強い向かい風や勾配の増加は必要トルクを押し上げるため、同じ速度を維持しようとするとケイデンスが落ち込みやすくなります。こうした状況でロー側の余裕があると、回転を守り、筋疲労の偏りを防げます。逆に追い風や緩い下りではトップ側の余裕が活き、ケイデンスを保ったまま速度を引き上げやすくなります。
実用的な微調整の進め方
- 走行ログでよく使う速度帯とケイデンスの中央値を確認します。
- その帯に複数の段が重なる構成を優先します。
- 登坂で目標ケイデンスを維持できない場面があれば、ロー端の歯数を2T単位で見直します。
- 下りや追い風で脚が回り切るなら、トップ側を1段伸ばすかフロント外側を大きくします。
これらを踏まえると、平坦で速度を刻むなら中段の密度、登りで脚を温存するならロー側の拡張が鍵であることが明確になります。最後は実走でのケイデンスの乱れ方を手掛かりに、段間差と端の余裕を少しずつ詰めていくのが効率的です。
ギヤ比とタイヤ径の組み合わせによる違い

同じギア比でも、タイヤの外周が変わるとペダル1回転で進む距離がわずかに変化します。外周が大きいほど1回転あたりの進行距離(開発距離)が伸び、同じケイデンスなら速度はわずかに高くなります。逆に外周が小さくなると、同じ回転数でも速度はわずかに低下します。この差は数パーセント程度ですが、巡航時のギア選択や登坂の負荷感、サイコン表示の速度・距離にじわりと影響します。
基本式と考え方の整理
ロードバイクで扱う量は次の関係でつながっています。
開発距離(m/回)= ギア比 × タイヤ外周(m)
速度(km/h)= 開発距離 × ケイデンス(rpm)× 60 ÷ 1000
ここでギア比はフロント歯数 ÷ リア歯数、タイヤ外周はホイールとタイヤの実測外周です。したがって、ギア比が同じでも外周が大きくなれば開発距離が伸び、必要なケイデンスはわずかに下がります。
サイズ別の外周と速度差の目安
700C(ETRTO622)で、タイヤ幅が増えると理論上の直径はおよそ幅の2倍だけ大きくなります。実走では空気圧やリム内幅で差が出ますが、概算の比較目安は次のとおりです。
| タイヤサイズ | 目安外周(m) | 外周差(25c比) | 速度例:ギア比2.8・90rpm(km/h) |
|---|---|---|---|
| 700×25c | 2.113 | 0% | 31.95 |
| 700×28c | 2.129 | +0.8% | 32.19 |
| 700×32c | 2.155 | +2.0% | 32.58 |
同じギア比2.8・ケイデンス90rpmでも、25cと32cのあいだで約0.6km/hの差が出る計算になります。数字は小さく見えますが、長距離の所要時間やケイデンス管理には無視できない差として表れます。
実走で感じる変化のポイント
タイヤを太くすると、外周増によるわずかな速度差に加え、接地面積の増加や空気圧の設定変更により踏み味も変化します。空気量が増えることで微細な振動が減り、同じギア比でも回しやすく感じる場面があります。一方、空力や路面抵抗の条件によっては、同じ速度域で必要な出力が微妙に変化し、結果として選ぶリア段が1枚違う、といったことが起きます。巡航中心なら外周増による開発距離の伸びが生き、登坂中心なら外周差よりも接地の安定感やトラクションの扱いやすさが効いてきます。
誤差を生む要因への配慮
理論外周からのズレは主に三つあります。第一に空気圧と荷重でタイヤがつぶれ、実効半径がわずかに小さくなること。第二にリム内幅の違いでタイヤ実測幅が増減し、幾何学的な直径が変わること。第三にブランドやモデルごとの成形差です。いずれも数ミリ単位の差ですが、外周換算では数十ミリ、速度で数パーセントに及ぶことがあります。サイコンの距離誤差や速度計の違和感は、これらの要因を調整すると解消しやすくなります。
セットアップの実用手順
タイヤサイズを変更したら、次の順で整えるとスムーズです。
- サイコンのタイヤ周長を更新する(取扱説明書の周長表ではなく、できれば実測値に置き換える)
- ギア比計算ツールやアプリに新しい外周を登録し、よく使うケイデンスでの速度帯を再計算する
- 旧タイヤ時の巡航ケイデンスと速度を基準に、リアのどの段が対応するかを対応表で確認する
- 実走で1〜2回の調整走を行い、巡航域の段間が大きすぎる場合はリアスプロケットの歯数構成を見直す
実測外周の簡易チェック
正確を期すなら、地面にバルブ位置で印を付け、体重を掛けた状態で1回転分を転がして地面の印間距離をメジャーで測ります。これが実効外周です。走行姿勢・装備重量・空気圧に近い条件で測ると、サイコンの距離・速度が実感に近づき、ギア比選択の基準が安定します。
セッティングの微調整の考え方
外周が大きくなって巡航がわずかに速くなった場合、従来どおりの速度で走りたいならケイデンスを2%程度下げるか、リアを1段軽くして回転数を維持する方法があります。逆に、登坂で重く感じるときは、中段より1枚軽い段を基準にケイデンスを70~90rpmの範囲に収めると、心拍や脚の負担が整い、ペース管理がしやすくなります。いずれも開発距離とケイデンスのバランスを見る発想が軸になります。
以上の視点を押さえておくと、タイヤ幅の変更は単なる乗り心地の調整にとどまらず、ギア比セッティング全体の最適化につながります。
初心者から上級者までのギア比の選び方

ギア比の最適解は、脚力だけでなく、よく走る地形、目標とするケイデンス、そして走行中に維持したい速度帯の三つの条件で決まります。ここではレベル別の考え方を土台に、最小ギア(登坂用)と中段の刻み(巡航用)、トップ側(伸び)の三点を数値で整える手順に落とし込みます。最終的な判断基準は、無理なく保てるケイデンスを長い時間キープできるかどうかです。
レベル別の基本方針
初級者は、まず疲れにくさと再発進の軽さを優先します。フロントは50/34などのコンパクトを前提に、リアは11-32や11-34を選ぶと、信号の多い街中や短い登りでもケイデンスを落としにくくなります。最小ギア比は1.1前後(例:34×32で約1.06)を目安にすると、心拍の乱高下を抑えやすくなります。
中級者は、ライドログのケイデンス中央値(たとえば80~90rpm)を把握し、その帯での段間差が細かいカセットを選ぶとペースが安定します。平坦主体で速度の揺れを減らしたいなら、14-15-16の連続がある配列が扱いやすく、トップ側は50/34×11-30や52/36×11-30などで十分な伸びが得られます。
上級者は、コースプロファイルと当日の風向・集団速度に合わせて端のギアを積極的に入れ替えます。平坦系のレースや高速巡航では52/36×11-28で中段の密度を確保し、山岳や激坂が長く続く日は34×34(比1.00)や34×36(比0.94)まで確保するなど、目的志向で構成を切り替えます。1×構成を用いる場合は、トップとローの幅は稼げても中段の段間差が広がりやすい点をあらかじめ織り込むと選択を誤りません。
最小ギア設定の数値目安(登坂用)
登りで失速しない基準は、狙う速度と保ちたいケイデンスから逆算できます。700Cの外周を約2.10mとすると、係数はおおよそ0.126です。
必要ギア比 ≒ 速度[km/h] ÷(ケイデンス[rpm] × 0.126)
- 勾配8%で時速10kmを80rpmで回したい → 10 ÷(80×0.126)≒ 1.0(例:34×34)
- 勾配6%で時速12kmを80rpmで回したい → 12 ÷(80×0.126)≒ 1.19(例:34×28)
- 勾配10%で時速8kmを80rpmで回したい → 8 ÷(80×0.126)≒ 0.79(ロードで確保するにはフロント小径化やワイドローが必要)
実際には風や路面で必要出力が変わるため、想定より一段軽い余裕を残すと、ペースを崩しにくくなります。長い登坂や疲労蓄積を見越すなら、目標比より0.05~0.10程度軽い最低比を確保する設計が現実的です。
巡航の要である「中段の刻み」を設計する
巡航の快適さは、中段の段間差の細かさでほぼ決まります。時速30km前後を多く使うなら、その速度帯に該当するリア歯数の並びで、1段あたりの速度変化が約1.5~2.0km/h以内に収まる配列が扱いやすくなります。具体的には、14-15-16-17の連続がある11-28や11-30の一部配列が有利です。11-34はロー側の余裕が増える反面、中段の一部で段間差が広がることがあるため、平坦主体の用途では候補から外す、もしくはフロントを52/36にして中段の回転域を補う、といった調整が有効です。
トップ側の確認(下りや追い風で回し切らないか)
トップで脚が空回りするかは、回したい最大ケイデンスでの到達速度を計算すれば判断できます。
到達速度 ≒ ギア比 × 0.126 × ケイデンス
- 50×11(比4.55)を100rpm → 約57km/h
- 52×11(比4.73)を100rpm → 約60km/h
- 52×12(比4.33)を100rpm → 約54km/h
普段の下りで55km/hを超える場面が少ないなら、50×11でも十分なことが多く、トップのためだけにフロント大型化を優先する必要は高くありません。むしろ中段の密度と最小ギアの余裕を先に確保する方が、平均速度の底上げに直結します。
実走での微調整ステップ
1回目の実走では、平坦・緩い登り・下りでそれぞれ1~2分間、目標ケイデンスを意識して走り、段間差が大きすぎる区間や回し切ってしまう場面をメモします。二回目はそのメモをもとに、リアだけ交換(11-28⇄11-30⇄11-34)で段間差を詰めるか、フロントを34⇄36⇄50⇄52で最小比またはトップ比を調整します。変速時のチェーン角度や変速性能の実感も考慮し、数値上の最適解と操作感のバランスが取れるところに着地させるのが現実的です。
拡張チェックリスト(観点と目安)
- 最小ギアで想定勾配をケイデンス70~90で維持できるか(1.00前後を基準に余裕を残す)
- 巡航域(例:28~35km/h)で1段ごとの速度差が2km/h以内に収まっているか
- トップで回し切らず、下りや追い風でも脚の回転で速度を伸ばせるか
- よく使う中段に連続した歯数(14-15-16など)が配置されているか
- タイヤ幅変更や空気圧変更後、外周とサイコン周長を更新しているか
- 1×採用時は中段の段間差拡大を許容できるか(コース次第でカバー)
以上を押さえると、ギア比は単なる数値の遊びではなく、疲労を減らして平均速度を上げる実用的な手段として機能します。狙うコースとケイデンスに合わせて、最小ギア・中段の密度・トップ側の三点を数値で整えることが、あらゆるレベルに共通する最短ルートです。